
湿地でみられる植物。 白い花穂が清楚で爽やかなヌマトラノオ。 黄色い可憐な小花を多数つけ、直立した草姿がしなやかなクサレダマ。小花が集まった咲き方に、野の花の優しさを感じます。花のつく、草の先端を切り取ったように和紙の柔らかな風合いで表し、短冊にあしらいました。
”Numatorao・ Yellow loosestrife”


湿地でみられる植物。 白い花穂が清楚で爽やかなヌマトラノオ。 黄色い可憐な小花を多数つけ、直立した草姿がしなやかなクサレダマ。小花が集まった咲き方に、野の花の優しさを感じます。花のつく、草の先端を切り取ったように和紙の柔らかな風合いで表し、短冊にあしらいました。
”Numatorao・ Yellow loosestrife”

夏から秋にかけて野原や土手、田んぼのあぜ道など日当たりの良いところで群生する姿が見られる、ツルボ。紅紫色の小さな花が集まって穂となって咲く姿が、可憐な野草です。ほかほかとした花の咲き方は、紅紫の花色を引き立て優美に見えます。ツルボの花穂は、公家が宮中に参内する時に従者に持たせた雅な柄の長い傘をイメージさせるところから、「参内傘(さんだいがさ)」とも呼ばれます。繊細な小花を和紙の繊維の強さと色合いで表し、短冊にあしらいました。
” Barnardia japonica ”

秋の風情を醸し出すシュウメイギク。楚々とした草姿で静かに季節を伝えます。すっきりとした印象の白い一重のシュウメイギクを和紙の抑えた光沢感と柔らかさで表し、短冊にあしらいました。
”Anemone japonica”

爽やかな高原の花、マツムシソウ。小花が多数集まって咲いたものが一つにまとまった、丸みのある頭花(とうか)という形状に特徴があります。薄紫の小花のひとつひとつと繊細な葉を柔らかな和紙で表し、短冊にあしらいました。
”Scabiosa japonica”

白鷺が舞うかのような優美で涼やかな夏の山野草。白い花色と繊細な花の構造が印象的な鷺草を和紙の白色と緑の和紙の柔らかな風合いによって表し、短冊にあしらいました。
“White Egret Flower”

夏の山野草より、蛍袋(ほたるぶくろ)と岩菲(がんぴ)の特徴を和紙で表し、短冊にあしらったものです。野の風情を伝えてくれる蛍袋(ほたるぶくろ)は、釣鐘状の花が可憐です。
朱紅色の鮮やかな花色が夏らしく、すっきりとした線を持つ岩菲(がんぴ)。ナデシコ科の植物らしい、花びらの切れ込みが優美です。それぞれの花の特性に合わせて和紙を選び、和紙の持ち味によって花の個性を表しました。
” Hotarubukuro・Silene banksia ”

夏の水辺を彩る半夏生(はんげしょう)。白い花穂に小さな花を咲かせます。葉の一部が白くなるところが涼しげな印象です。
初夏から夏の夕暮れに儚い一日花を咲かせる月見草。江戸時代の末に渡来したとされる月見草は、咲き始めは白い花を咲かせ、しぼむと紅色に変化します。
それぞれの花の特徴を、数種類の和紙の取り合わせによって表し、短冊にあしらいました。
“Lizard’s tail・Oenothera tetraptera”

梅雨にかかる季節に咲く植物を和紙の花で表したものです。
上から、岩絡(イワガラミ)・小紫陽花(コアジサイ)・糊空木(ノリウツギ)・七段花(シチダンカ)・八重蕺草(ドクダミ)の野趣ある5つの花を選びました。
イワガラミは、岩や樹木にからみつき、高い壁をつくるように広がり、白い花を咲かせます。装飾花を一片しかつけないところに特徴があります。
コアジサイは、ひらひらした装飾花はなく、細かい花が集まった両性花(りょうせいか)のみで構成されています。
ノリウツギは、白い花穂(かすい)が立体感ある円錐状に広がります。
シチダンカは、ガクヘンが重層的にまとまった八重咲の華やかさがあります。
ヤエドクダミは、白い花弁のようにみえる葉が変化した苞(ほう)の重なりが清楚です。
湿度の高い梅雨にかかる時季を好む花たちは、潤いを得た緑深い山野を彩ります。5つの植物を和紙の持ち味を生かし、それぞれの特徴を出しました。
”climbing-hydrangea ・Hydrangea hirta・Hydrangea paniculata・
Hydrangea serrata・Houttuynia cordata”
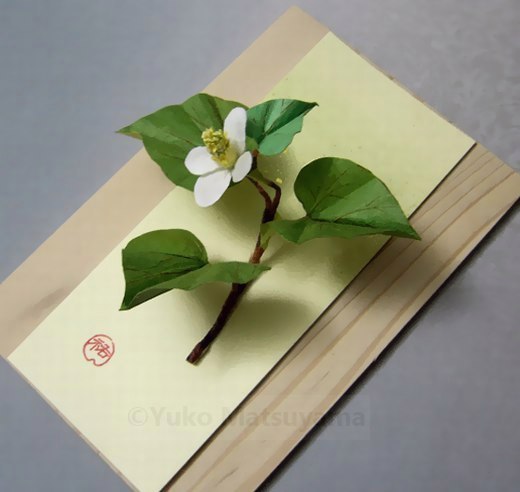
身近な夏の花、ドクダミ。白い花弁のようにみえる葉が変化した苞(ほう)は、清々しい印象で目をひきます。すっきりとした素朴な野の花の風情を手漉き和紙の繊維を生かして表し、短冊にあしらいました。
“Houttuynia cordata”