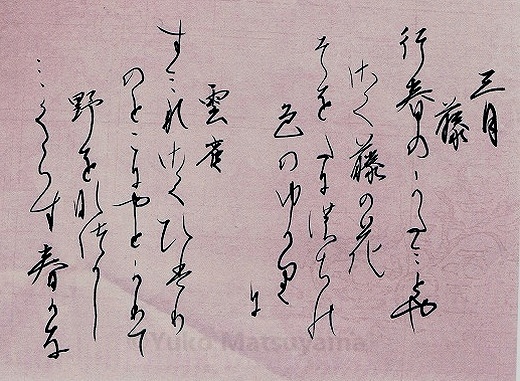桃山時代から江戸初期、書・陶芸・漆芸・出版など多彩な分野で活躍した琳派の始祖である本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)。2015年、1615年(元和元年)に光悦が徳川家康より京都の洛北の鷹ヶ峰(たかがみね)の地を拝領してから400年経ちました。鷹ヶ峰は、丹波・若狭と山城(京都)を結ぶ重要な出入り口の一つとなっていました。光悦が京の中心から移され、鷹ヶ峰の地を拝領した経緯や家康の真意は明らかでありませんが、光悦が師と仰いでいた古田織部の自刃に関わりがあると思われます。
鷹ヶ峰を拝領したのと同じく1615年(元和元年)、大坂夏の陣の折に大坂方に内通した嫌疑をかけられ、織部は自刃に追い込ました。このことによる光悦の鷹ヶ峰に移住後の心境の変化は、書の題材として雅な和歌から、中国の古典、『楚辞(そじ)』にある屈原(くつげん)の孤高を象徴する詩とされている「漁夫辞(ぎょふのじ)」を好むようになっていったところに現われています。
光悦が木工、金工、漆工、蒔絵、螺鈿(らでん:貝細工)などの工芸技術を持った人々を結集しさせ制作に関わったと伝えられている『樵夫蒔絵硯箱』 (きこりまきえすずりばこ:静岡・MOA美術館所蔵)で能の謡曲『志賀』が主題とされている背後に硯箱の内側で清らかな春を芽吹きの「蕨」と「蒲公英」(たんぽぽ)の葉に託したものがあると「光悦と春草」 で書きました。
光悦以後、琳派の系譜の春の主題として、尾形光琳(おがたこうりん)、尾形乾山(おがたけんざん)、酒井抱一(さかいほういつ)、鈴木 其一(すずき きいつ)、神坂雪佳(かみさかせっか)に至るまで芽吹きの美しさとして注目されたのが「蕨」です。「蕨」を描いた素朴で清らかな姿からは、万葉集の「いはばしる垂水の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも」(志貴皇子:しきのみこ)の歌も想い起されます。
また、「蕨」からは司馬遷の『史記』伯夷列傳(はくいれつでん)第一 巻六十一にある物語が想起されます。
伯夷・叔斉(はくい・しゅくせい)は、殷(いん)の孤竹(こちく)国主の王子でした。父は、弟の叔斉を後継に選びます。父の亡き後、弟は兄を差し置き王位につくことを望まず、兄に王位を譲ろうとしますが互いに譲り合い、遂に二人ともに国を出奔します。その後、周の武王が殷の紂王(ちゆうおう)を討とうとした時、伯夷・叔斉は臣が君主を攻め滅ぼすことの非を説いて諌めますが聞き入られられず、殷は滅び周が天下を統一しました。伯夷・叔斉は、周の天下となった国で禄を食(は)むこと恥じて首陽山に隠れて蕨をとって食べて、ついに餓死したという伝説です。『史記』に伝えられた伯夷・叔斉の兄弟は、清廉潔白の人のたとえとされています。「蕨」は、清廉潔白の象徴ともいえます。
『樵夫蒔絵硯箱』の制作経緯は定かではありませんが、硯箱の中の蓋裏(ふたうら)・見込(みこみ)にある「蕨」には、古歌、故事などに託されてきたメッセージが込められていると思われます。
琳派の系譜を通じて「蕨」は春を象徴し、光悦の想いを継承する重要な主題となったと考えます。その一例として光悦没後200年ほど経て、鈴木 其一は『漁樵図屏風(ぎょしょうずびょうぶ)』で右隻に光悦の『樵夫蒔絵硯箱』から取材した樵(きこり)の歩く姿を描きました。樵の歩く道の傍らには蕨が描かれています。左隻は、紅葉の渓流を背景にした漁夫が描かれています。古来より「漁樵図」には中国より伝わった隠逸の思想が背景に込められてきました。『樵夫蒔絵硯箱』を想い起す、蕨の芽吹きがさりげなく描かれている清らかで瑞々しい春の景からは、光悦への想いが伝わってきます。
画像は蕨の芽吹きを和紙で縮小して表したものです。高さは、7.5cmほどです。
”Bracken”
2016 1/27~2/2